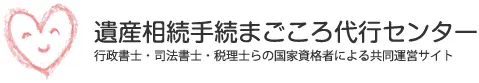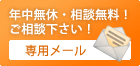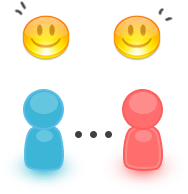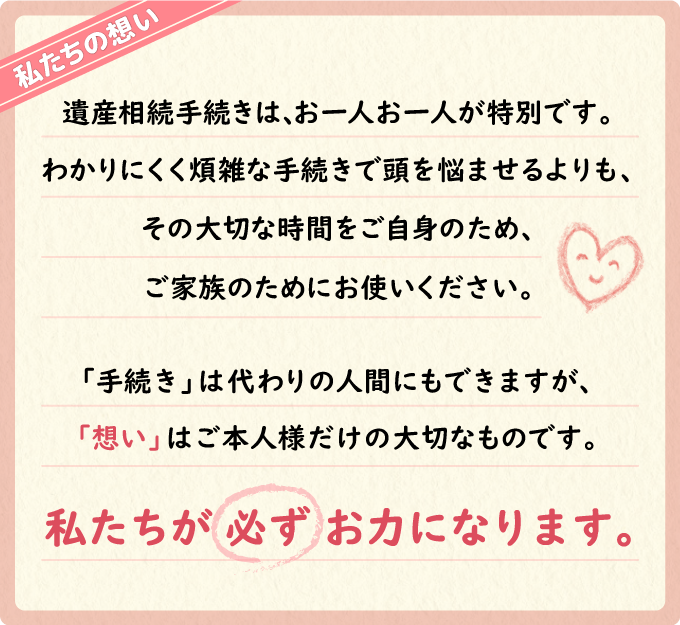今回のご相談のように、相続人ではない人が、看護や介護をするというケースは決して珍しいことではありません。
ですが、こうした「相続人ではない人」がどれだけがんばっても、その人は何も相続できないというのが民法の規定です。
とはいえ、それではやはり、尽くしてきたご本人としては腑に落ちないというか、やりきれない気持ちになりますよね…。
そこで今回は、2019年7月1日に施行された「特別の寄与」の制度について、制度の概要なども含めてご紹介したいと思います。
目次【本ページの内容】
1.特別の寄与の制度とは
この制度は、被相続人(亡くなった人)に対する介護や看護をされてきた方への苦労、いわゆる” 被相続人への寄与 ”を遺産分割に反映させようといった主旨で創設されました。
というのも、そもそも相続権は、戸籍上の法定相続人に該当する人のみに生じるものです。
つまり、どれだけ近くで最期まで介護に努めた方であっても、相続権が生じていないと相続されない、わかりやすく言うと、被相続人との関わりの深さ(=寄与度)は無関係ということです。
被相続人が遺言書を残していたり、生命保険をかけていればその内容に従って財産を引き継ぐことができるのですが、例えば夫の両親の介護をしていた人が「遺言書を書いてほしいです」とはなかなか言えないですよね。
そんなことを言おうものなら「あなたは財産を狙って介護をしているの!」という大喧嘩にもなりかねません。
そこで、戸籍上の相続権がなかったとしても、被相続人への寄与を遺産分割に反映させよう!というのがこの制度の主旨です。
法務省のパンフレットにもわかりやすく記載されておりますのでこちらもご参照ください。
1‐1.「特別の寄与」制度の概要
改めてこの制度を簡単にご説明しますと、相続人ではない親族が被相続人に寄与した場合、相続の恩恵が受けられるようになる制度です。
かなり崩した表現ですので勘違いされるかもしれませんが、「恩恵を受ける」というのは「相続人になる」わけではなく、また被相続人の財産を直接請求できるわけでもありません。
「特別の寄与」をした相続人以外の親族は、遺産を受け取った人に対し、寄与に見合った金銭を請求することができます。
この請求できる金銭のことを「特別寄与料」といいます。
つまり、この「特別寄与料」が介護・看護をねぎらう報奨に値するということになります。
尚、この特別寄与料を請求できる親族の範囲は6親等内の血族及び3親等内の姻族に限られます。
6親等?血族?3親等?姻族?という声が聞こえてきそうですが、本人から見て両親が1親等、兄弟姉妹が2親等、甥姪が3親等ですので、6親等というとかなり広いところまで範囲に含まれます。
姻族というのは婚姻相手の親族のことで、そちらは実際の血のつながりがない関係ですので、血族の6親等に比べて半分の3親等までとなっています。
よって、古くからの友人でずっと面倒見ていたという方は、残念ながら寄与者にはなれないということです。
2.「特別の寄与」4つのポイント
さて、制度の概要がわかったところで、次は制度のポイントについてご説明します。
- 相続や遺産分割はこれまで通り相続人だけで行う
- 特別の寄与をした寄与者が相続人に対して金銭を請求する
- 話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申し立てることができる
- 相続人が複数いる場合、各相続人の“相続割合=負担割合”になる
2-1.相続や遺産分割はこれまで通り相続人だけで行う
相続人が複数いる場合、やはりいろいろな感情が皆様ありますので、遺産分割協議がスムーズに進まないケースもよくあります。
(当方にはそういったトラブルのご相談も多いです…)
そこに「寄与者」という”相続人ではない”人が介入するとなると、さらに状況は複雑になるのは目に見えていますよね…
しかし、寄与者は相続人になるわけではなく、相続人に対して特別寄与料を請求できる権利を持つだけです。
もちろん寄与者に対してどれだけの特別寄与料を支払うのかということは相続人の中で協議すべき事項ですが、そもそもの遺産分割協議に寄与者が参加するわけではありませんので、その点はお間違えのないようにしてください。
寄与者は「相続人」ではありません。
2‐2.特別の寄与をした寄与者が相続人に対して金銭を請求する
ポイント①とも少し重複しますが、寄与者は「相続人」ではありませんので、遺産分割協議に参加するのではなく、寄与者自身が相続人に対して特別寄与料を直接請求する必要があります。
では、特別寄与料はどれぐらい請求できるのかと申しますと、
具体的な決まりはありません!
(期待させるような書き方をしてすみません)
よって、相続人と寄与者の双方で、寄与の程度や期間、遺産の総額などを勘案して決めることになります。
2-3.話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申し立てることができる
さて、特別寄与料は相続人と寄与者の話し合いで決めるとお伝えしましたが、元々相続権がない人が相続人に対してその相続財産の一部を請求する訳ですから、すんなり「どうぞ(笑顔)」と譲ってくれないかもしれません。
寄与者は「長かった…辛かった…大変だった…」と今までを振り返りながら、自分のやってきた頑張り、努力、苦労に相当すると考える金額を伝えるわけです。
それに対して相続人は「面倒を見てくれたのは感謝しているけど、お金に換算するならまぁこれぐらいじゃないかな」と自分の考える金額を支払おうとするわけです。
お互いの想いがそれぞれ違う方向を向いている時点で
納得できない!!
と、なりそうな気がしませんか…?
このように、相続人と寄与者が話し合いが付かなかった場合、寄与者は家庭裁判所に審判を申し立てることができます。
話し合いで決まらないなら裁判所に決めてもらうということですね。
ただし、この審判請求には期限があります。
その期限とは、
被相続人の死亡及び相続人を知ってから6か月以内
または
被相続人の死亡を知らない場合でも死亡から1年以内
と定められています。
「死亡を知らない場合でも」死亡から1年以内というのは少し短いと感じられるかもしれませんが、「特別な寄与をしてきたような人が死亡の事実を1年も知らないなんていうことがあります?」という意味の1年という期限なんでしょうね。
たしかに「特別」というぐらいの関係ですので、1年も死亡の事実を知らない時点で関りがすごく薄そうに感じますよね。
2-4.相続人が複数いる場合、各相続人の“相続割合=負担割合”になる
相続人が複数いる場合、各相続人は、特別寄与料の額に自身の相続割合を乗じた額を負担します。
少しわかりにくいので、例を用いてご説明しますね。
【例】
相続人 :妻、子A、子Bの3人
相続割合 :妻(2分の1)、子A(4分の1)、子B(4分の1)
特別寄与料:100万円(合意済)
この場合、妻と子A、Bそれぞれの負担割合は下記のとおりとなります。
【特別寄与料の負担額】
A:100万円×1/2=50万円
B:100万円×1/4=25万円
C:100万円×1/4=25万円
今回のご相談者様は、この制度及び期限について知らなかったため、ご相談をいただいたときはすでに死亡日から4か月経っていました。
お姉様のお子様にこの話をされたところ、良心的に応じてくださり、特別寄与料を受け取ることができたとのことです。
苦労が報われる、まさにそんな制度だと言えますね。
3.特別寄与料と相続税申告
特別寄与料の額が決定すると、特別寄与料を被相続人から遺贈によって取得したものとみなします。
請求する相手は相続人なのに、相続人から寄与者への「贈与」ではなく、被相続人から寄与者への「遺贈」なんです。
※「遺贈」は相続人以外の人が相続財産を受け取る場合に使われる言葉で、広い意味では「相続」と同じニュアンスで読み取っていただいても差し支えありません。
よって、相続税申告がある場合、特別寄与料にも相続税が課税されます。
要は、相続財産の一部なので、やはり相続税の対象ということなんでしょうね。
では、特別寄与料にかかる相続税の申告・納付の期限はと申しますと、特別寄与料の額の決定から10か月以内と定められています。
本来の相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」ですので、同じ10か月であってもスタートの日付が違う点にご注意ください。
では、特別寄与料を支払った相続人は、相続税申告において特別寄与料をどのように扱うのでしょうか?
これはもう普通に考えればわかると思いますが、特別寄与料を支払った(または支払うことになった)相続人は、相続税の課税価格から特別寄与料を控除することができます。
言い方が少しわかりにくいですが、例えば4,000万円を相続しました→特別寄与料は500万円です→残りの3,500万円に対して相続税が課税される、こういった考え方ですね。
また、相続税の申告が終わった後に特別寄与料を支払うことになる場合もあるでしょう。
その場合、申告から4か月以内に更正の請求をして、払い過ぎた相続税の還付を受けることができます。
4.まとめ
- 特別の寄与の制度とは、相続人以外でも被相続人への寄与度に対して相続の恩恵が受けれるようになった制度である
- 遺産分割協議には関与することができないが、相続人に対して特別寄与料を申し出ることができる
- 特別寄与料の申し出(請求)には期限がある
- 相続税の申告が必要な場合、寄与者は課税対象となり、相続人は控除対象となる
法律というのは時代のニーズや文化、社会、多様性などに応じて改正されるべきものですし、現にこうして大きな法改正がありました。
皆様に発生している権利をしっかり主張できるように、疑問やお困りごとなどございましたらお気軽にご相談ください。